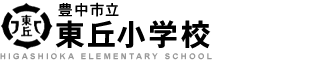7年に一度の…
10月の25日・26日の2日間、”大阪府人権教育研究豊能大会”という7年に1度の人権大会がありました。
『何が7年に1度?』かというと、大阪府は各地区(豊能・三島・北河内など)に分かれており、1年ごとに主催地区が移り変わっていきます。なので、ホスト地区が7年に1度回って来るという、教育界でいえばサッカーワールドカップと野球のWBCを合わせた”7年に1度”の機会でした。全体会・分科会2日間で延べ2000人を超えるほど参加者があり、活発な意見や質問も出されていました。
それだけ大きな大会ゆえ、準備期間も2年を要し、その準備してきたものがすべて2日間にギュッと詰まっている感じでした。東丘の教職員も、他校や他地区の実践にふれ、学ぶことや感じることがたくさんあったのではないかと思います。


日本という単位で考えると、思いやりの国、モラルやマナーの国というイメージが浮かぶのではないでしょうか?なので、もちろん人権意識も高い…と。
しかし、実は世界的に見ると日本の※人権意識はそんなに高くありません。部門によれば下位に沈んでしまう項目もあります。
更に言うと、世界では企業の「人権リスク」に対して厳格に対処するためのルールづくりが着々と進んでいるようですが、つい最近まで、日本企業の「人権」対応の取り組みは、とても遅れていたようです。国際NGOが発表している人権対応スコアでは、名だたる日本を代表する企業が軒並み「ほぼ0点」の扱いを受けているそうです。国連の持続可能な開発目標(SDGs =サステナブル・ディベロップメント・ゴール)の各項目に対する意識調査によると、日本は「人権」に対する意識が希薄だとされています。(日経ビジネス引用)
※人権意識とは、人権感覚と人権に関する知識や技能を一体化し、人権尊重の意義を理解して偏見を排除し、差別や不合理性を認識できる判断力、自分自身で対応しようとする意思を指します。
以上は大人の世界です。
今回、いつものように5時間・6時間授業をこなしていては全く間に合わないので、5・6時間目を割愛して教職員の参加を勧奨しました。そのいただいた時間の分、子どもたちが世界的にも通用する人権意識を身に付けることが出来るよう、『大人教で学んだことを子どもたちに還元する』ことが叶えばと思います。
そういえば今週は人権参観です。ご来校をこころよりお待ちしています。