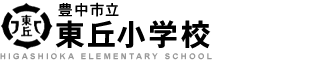‟未来を切り拓くチカラ”とは…
八中・北丘・東丘の3校では、『探究学習』について学びを進めています。
8月には大阪高校の山原教頭先生と和田先生をお招きし、大阪高校で取り組まれている探究科の探究学習の授業を、我々教職員が自ら体感する側となって学びました。大阪高校の実践を通して小学校から高等学校までのキャリアが少しイメージできたように思います。そして、高等学校⇔中学校⇔小学校の校種間連携も図ることが出来たのではないかと実感しています。(ご多用の中、平野校長先生にも応援に駆けつけていただきました。ありがとうございました。)


『探究的な学び』と聞けば、何となくイメージは出来ると思いますが、”問題解決学習”改め”問題《発見》解決学習”でしょうか。
その学びを広げ深めるため、秋田大学名誉教授・東京未来大学特任教授である阿部昇先生を東京からお招きして講義いただきました。秋田県はいち早く”問題解決学習”に《発見》を盛り込み、探究学習を長く実践を重ねていることもあり、私たち自身が‟探究者”として学ぶことができました。やむを得ず学校を離れることが出来ない職員も参加できるよう、3校の距離を‟0(ゼロ)”にするオンラインで中継を結びました。(阿部先生は台風15号の影響で新幹線が大幅に遅れ、大阪で通り過ぎたはずの台風を追いかける形で東京に戻られました。本当にありがとうございました(_ _))

これはあくまでも私個人の見解ですが、『探究学習』において山原・先生からは左右に広がる横のベクトルを、阿部先生からは高くも深くもある縦のベクトルを学び、”探究”のイメージがより明確になってきたように感じています。あとは学校の特色ある学びを奥行きとするならば、子どもたちの『探究的な学び』は3次元に収まらず4次元へと自由に飛び出していくような感じかと…。
我々は職業柄、学習には【めあて】があって【まとめ】があるので、学びがまとまらなかったり末広がりになったりすることは少し苦手です。しかし、自らの学びを広げ深めることが”探究”だとしたら、そんな固定観念を取っ払って柔軟に学びを進めることも大切なのかもしれません。
そして、3校の学校目標にある『未来を切り拓く』、それは”探究”に近いのかもしれません…。