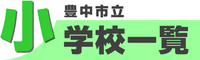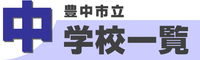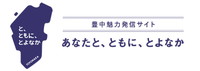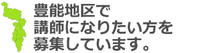桜井谷小学校 公開授業研究会(2023/10/31、2023/12/05)
豊中市立桜井谷小学校は、昨年度から豊中市校内研究推進事業「情報活用能力の育成」を受け、
『 伝え合い 受けとめあい 認め合う子 』「自分の考えを持ち、伝え合う子どもを目指して」
を研究主題に、研究を進めています。
今年度は10月31日(火)に2年生、12月5日(火)には6年生にて公開授業研究会を実施しました。

桜井谷小学校 公開授業研究会(10/31) 2年生 体育
2年生では、これまで「ドン技」、「バン技」、「ピタ技」と名付けた跳び箱運動の技を習得してきました。
まずはタブレットは置いて、準備運動、場づくり、前時までの復習をしました。


普段から活用しているので、タブレットを取ったら、すぐにそれぞれが SKYMENU Cloud を開いて準備していました。
ノートがすでに配布されているので、まずそれを確認すると、いよいよペアで技を撮影し合います。

「いいよ!」と声をかけられた相方さんは、勢いよくチャレンジスタート!跳ぶ様子を動画で撮影してもらうと、すぐに一緒に動画を確認。

今度は全体で集まり、先生が上手に跳べている児童の動画を紹介。
「ドン!パン!ピタ!」をスローモーションで確認しながら、アドバイスをします。

自分たちが撮影した動画を見直して、「ドン」「パン」「ピタ」でどれが上手にできていたか、どれが苦手かを確認。
最後にもう一度、自分の得意や苦手を意識しながら合体技に挑戦!撮影した動画は、教室で先生に提出して、授業は終わりました。

事後検討会では、「体育科の学習で、ICTが活躍する活動はどのようなものがあるか。また、活用の仕方。」を討議の柱に、検討を進めました。
そして最後に、 大阪教育大学附属池田小学校 澤田 崇明 先生 より、お話をしていただきました。
運動遊びの段階では、運動遊びの楽しさに触れながら活動を深めるというよりも広げていくことが大切だと助言いただき、ICTを活用した体育実践についてのヒントを多数いただきました。
【 体育科におけるICT活用の利点3つ 】
- 見えないものを見える化できる ex) 遅延再生ビデオ・動画で見比べる・音で測る
- 思考・判断・表現を見取ることができる ex) 実況中継・解説・データ持久走・ベストプレー
- 時短・マネジメント・評価につながる ex) 動く的を狙って・動画で振り返り・動画を提出
桜井谷小学校 公開授業研究会(12/05) 6年生 国語
6年生では、国語の「話し合って考えを深めよう」の単元で
「グループプレゼンをしよう!」というめあてのもと、ここまでの予選大会を勝ち抜いたグループごとの プレゼン対戦 に取り組みました。

司会者はタブレットを使ってタイムキーパー役も担いながら進行を務めます。
それぞれの発表はPMI表(P:プラス、M:マイナス、I:面白い)を用いて、みんなで評価をし、勝敗を決定します。


第一グループは「社会に出てより役に立つのは?」をテーマに、国語、英語、算数の三チームに分かれて対戦を行います。
第二グループは「家族で外食するなら?」をテーマに、洋食、和食、イタリアンの三チームに分かれて対戦します。
各グループごとに、シンプルプレゼンを使って根拠を元に自分たちの主張を論理的に伝えていきます。今回は、シンプルなプレゼンテーションを心がけることや「話すこと」に重点を置くという視点からあえて PowerPoint ではなく、シンプルプレゼンを選びました。
シンプルプレゼンには、文字数が制限されているからこそ情報を精選する必要性があるという良さがあります。
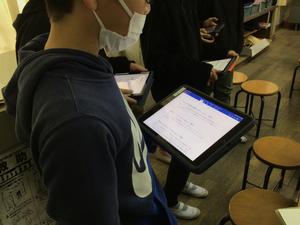
シンプルプレゼンでプレゼンテーションを見せながら、一人ひとりが話す台本には Word を用いて発表を進めていました。
発表では、それぞれのチームが自分の主張する考えをより良く見せることができるように工夫したシートを作っていることが伝わってきました。
発表を聞く児童は、PMIシートに発表者の主張を項目わけして記録し、評価へと繋げます。

意見交流の時間になると「○○の点についてなんですが…」という指摘に対して、グループで頭を寄せ合い、プレゼン資料に立ち戻り、すぐにテレビに答弁したいページを掲示すると「○○の点については…」と答える姿もありました。
事前学習では、一人ひとりが役割分担をしてタブレットを活用しながら調べたそうです。他のグループから出た質問に対して、一人ひとりが根拠を持って答えている姿から、それぞれのグループがしっかりと事前に調べた上で発表している様子が伝わってきました。
最後には、記入したPMIシートを元にグループ内で意見交流をし、一人ひとりが発表したチームのいいところを付箋に記入し、前の画用紙に貼り付けにいきます。
対戦の結果は次回発表。一番説得力のあるチームがどこなのか、子どもたちも結果が待ち遠しい様子でした。
机上にはタブレットとワークシート、付箋、そしてノートがあり、タブレット活用だけを中心に据えるのではなく、アナログの作業とICT活用とをハイブリッド化させて授業を進める様子が見られました。
事後検討会では、 池田市立神田小学校 樋口 綾香 先生 より、お話をしていただきました。
まずはじめに、樋口先生は 「何を願って国語授業づくりをしているか」 と問いかけられました。
目標がないと、子どもたちにつながっていかない、
- 子どもの考えがつながること
- 言葉が豊かになること
- 教材の中で新しい発見をすること
これらを叶えていくためには、何よりも日々の授業が大切だというお話に始まり、たくさんのご助言をいただきました。
主体性とは「自分の意思に基づき、自分の判断で行動しようとする態度」のこと
樋口先生は、教育課程(カリキュラム)に則って学ぶことを考えることは大前提として置きながらも、 そんな「カリキュラムに則った授業を少しでも面白くしよう!」と日々考えておられるとおっしゃっていました。
「その結果として、子どもたち自主性を育むことを目指したい」と、下記の三つを整えていくことの大切さを教えてくださいました。
「子ども理解」→単元計画・授業づくり、教材・言語活動の設定
「教材理解」→教材分析・学習者研究 1年間・6年間のつながり
「学習環境」→学び合う・高め合える仲間 学び方を選択できる・確かめ合える環境
他にも、「探求の学習サイクル」と「気づき→情報収集・整理分析→まとめ・発表→ふりかえり」を重ねていくことの大切さや
指導言の有効性(発問・指示・助言・指導・評価)、話し合う力(広げる・整理する・深める)、三角ロジック(主張・根拠・理由)についてなど、
時間内には収まりきらないほどの充実した学びをいただきました。
2年生と6年生の発達段階に応じた、タブレット活用の有用性や可能性について深く考える貴重な機会となった実践研究会でした。