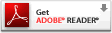マチカネ先生塾 12期生 第9回 『 授業基礎力養成講座③ 教科等(読書活動)』(2025/2/15)
マチカネ先生塾第9回目『 授業基礎力講座③ 教科等(読書活動)』(2025/2/15)
今回は授業基礎力講座③として豊中市教育委員会事務局読書振興課より3人の講師の先生をお招きし、読書活動についての講話・演習をいただきました。
まず、『公共図書館がささえる、「ふだん使いの学校図書館」』をテーマに、豊中市の学校図書館としての特色について分かりやすくお話していただきました。豊中市の特色の一つに、全市立学校に専任の学校司書を配置している事があります。これは大阪府下でも非常に珍しいことです。システム・物流等の環境整備の面において豊中市は読書活動を推進していくシステムが整っています。その他、学校図書館を活用した授業実践事例の紹介がありました。
次に、図鑑の利用指導について説明していただきました。
図鑑の使い方で押さえておきたいポイントは、目次や索引を活用することです。これらを上手に活用することで情報を早く見つける事ができるようになっていきます。
そして、本の扱い方についても教えていただきました。子どもたちが本を丁寧に扱うように教えていくことも読書活動を進める時の教師の役割の一つです。

続いて、「読み聞かせをしてみよう」ということで、はじめに講師から絵本の読み聞かせと実践的な内容の講話がありました。
絵本は、絵と文章との調和によって構成されている、いわば一つの芸術作品です。読み聞かせをしてもらうことで、文章を聞きながら絵をじっくり見て楽しむことができます。だからこそ、大人はもちろん、特に子どもたちにとっては、読み聞かせは絵本を味わうのに適した方法になります。
● 集団への読み聞かせの本を選ぶときには、次の3つのポイントに気をつけます。
① 本の大きさ
② 絵の細かさ
③ おはなしの長さ
⭐︎ 絵本としての評価とは別に、集団への読み聞かせには、向く本と向かない本がある
⭐︎ 読み聞かせをする相手のことを思い浮かべて本を選ぶ
⭐︎読み手自身が好きな本、おもしろいと思う本を選ぶ
また、先生として、子どもたちに大切なメッセージを伝えたいときに、絵本や読み聞かせを使ってコミュニケーションを取ることもできます。
さて、いよいよ読み聞かせ体験です。
まず好きな本を1冊ずつ選んだ後、読み方についてのレクチャーを受けました。
その後の体験では、塾生のペア同士で一生懸命取り組み、先生方からアドバイスをいただきました。




最後は、みんなでアニマシオン体験をしました。アニマシオンとは、モンセラ・サルトさんが考案した、子どもが読書好きになるように導くための読書の指導メソッドです。「読書へのアニマシオン75の作戦」という本では様々なアクティブな読書方法が作戦として紹介されています。
今回はその中の3つの作戦にチャレンジしました。
①作戦47「これが私の絵」作戦58「みんなで一つの詩」:『俳句の絵本』(坪内稔典/監修 くもん出版 2013)
②作戦55「聴いたとおりにします」:『にんじんさんがあかいわけ』(松谷みよこ/ぶん 童心社 1989)
③作戦38「ここに置くよ」:『ぶたぶたくんのおかいもの』(土方久功/ぶん・え 福音館書店 1970)
仲間同士で分かり合えたり、演じる中で自然と協力したりと、笑顔がいっぱいの時間となりました。


一口に読書といっても、味わい方から伝え方など、読書の奥の深さを体感しながら学ぶことのできた第9回となりました。