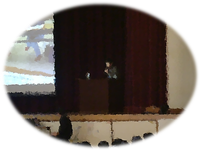1年防災教育(泉丘自主防災組織について)
昨日1年生は「防災教育」の一環として、地域の泉丘自主防災組織の方にお越しいただき、地域防災について講演をいただきました。
昨年夏に南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されるなど、南海トラフ地震発生への注意を忘れるわけにはいきません。そこで、1年生では「自分のいのちを守るための自助、地域とつながり互いのいのちを助け合う共助」について理解を深め、いざというときにどのように行動するのかを学び、意識を高めていく取り組みを行っています。
いままでの取り組みは
5月:第1回避難訓練(校内の避難経路・危険個所の確認)
6月:災害発生時の意識調査(防災アンケート実施)
7月:とよなか防災アドバイザーの派遣制度を活用した専門家の講演
9月:第2回避難訓練(地震を想定し、未告知の避難訓練)
10月:救急救命講習(万が一に備え大切な人の命を守るため、心肺蘇生法、AEDの操作を体験)
11月:ボランティア体験(高齢者体験、車いす体験、白杖体験を実施し、災害発生時の観点から自分たちができる必要な配慮や支援を考える)
これらの取り組みのまとめとして、昨日地域(泉丘)自主防災組織について講演をいただきました。
*内閣府の「首都直下型地震」の映像・・・地震がいつ、どこで起こるかわからないこそ地震への備が必要
*その備えとしての「自主防災組織」
①いざという時どうする?
・泉丘フローモデルについて説明いただきました
・第一に自宅や自宅周辺で「自助」(自分自身と家族の身を守る)。「共助」(ご近所や周辺地域の安全確認や救助)の活動、そして泉丘小学校へ集合し、「泉丘災害対策本部を設置」
・自主防災組織と各地域団体とが連携し、手助けを必要とする方の「安否確認作業」を開始
②避難所開設へ
・避難所の組織を説明いただきました。
・体育館へ避難者が多数来られた場合、組織がないと運営ができません。そのために6つの係を決めています(総務係・情報係・物資係・衛生係・要援護者係・食料係)
*今年は阪神大震災から30 年の年。豊中市は1月18日全自主防災組織を集めて「同日の一斉訓練」を実施しましたが、泉丘自主防災組織の取り組みを、ビデオを見ながら説明いただきました。豊中市消防局の「消火器体験」「AED 体験」、豊中市下水道局の「給水車体験」、豊中警察の「災害救助犬」の訓練実演。警察と提携しているドローンの会社から、テントの中でドローンを飛ばす体験や、プロが大きなドローンを運動場で飛ばす実演。また煙の中を進む避難訓練、障害物がある道を歩く体験、仮設テントの展示、それから炊き出し(豚汁)の配給など様々な体験がありました。最後にメッセージとして「どんな形でもいいので、こんな機会に一人でも、少しでも関わって、防災を考えていただきたいですね。」とのことでした。
また、次のようなお話もいただきました。
「2018 年6 月18 日午前7 時58 分の大阪北部地震の時、中学生のみなさんや小学生も登校時間でした。大きな揺れにみまわれ、学校の近くまで登校していた一部の第17 中生たちが同じく登校中の泉丘小学校児童に中学校グラウンドへの避難をさせました。揺れがおさまるまで避難し、その後泉丘小学校まで登校について行ってあげました。この話を聞いた時は地域の大人は感動しました。」