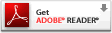マチカネ先生塾 13期生 第5回
11月8日(土)第5回マチカネ先生塾が庄内体育館で行われました。
今回のテーマはコミュニケーション力養成講座③「子どもと遊ぼう(なわとび)」でした。講師に豊中市立豊島西小学校の金森校長先生をお招きし、なわ跳びの実技を通して、さまざまな跳び方の学びだけでなく、子ども同士の繋げ方やクラスの一体感づくりなどについても学ぶ機会となりました。
まずは準備体操。受講生が一人ずつ体操を考え、みんなで体をほぐしました。

さあ、いよいよなわ跳びの実践です。その前に、なわの持ち運び方について、たすきがけのように体にかける方法を教えていただきました。こうすると、もし転んだりしてしまっても両手が空いているので安心です。なわ跳びというと、いろいろな技ができるようになることに目が行きがちですが、こういった視点も教えていただけたのは受講生にとっても貴重な学びになったのではないでしょうか。
【実践した一人技】
①前まわし跳び
一回旋一跳躍(よくある前まわし跳び)と一回旋二跳躍(二拍子跳びともいいます。なわを一回まわす間に二回跳ぶ跳び方)。
②交差跳び
③あや跳び
④けんけん跳び
このあたりの技は皆さん慣れたもので、上手に跳んでいました。

⑤返し跳び(跳ばないなわ跳び)
これは難しい技で、「初めて知りました。」という受講生も多かったです。この技は時間をとって円になって教え合いました。その中で、できるようになった人を中心に教え合いをする姿がありました。金森先生も、「自分ができるようになる喜びはもちろん、自分が教えて友だちができるようになる喜びもある。」とおっしゃっていました。そういった活動の積み重ねが集団の雰囲気をよくしていくこともあると、実感をもってわかってもらえたのではないかと思います。

続いて二人以上で協力して跳ぶなわ跳びです。
【実践した二人技】
①向かい合って、一本のなわで前まわし跳び
②同じ方向を向いて、一本のなわで前まわし跳び
③同じ方向を向いて、隣同士で前まわし跳び(マクド跳びというそうです)
【実践したグループ技】
トラベラー(二人技の②を、全員で順番に行います)
一人で跳ぶ時と違い、タイミングを合わせないといけないので、より難しくなります。自然と、「せーの!」などの声が聞こえてきました。そして、できた時の嬉しさも一人技より大きく、また、みんなで分かち合えることも良さです。また、成功させるために、いろいろな声掛け・会話が生まれていました。「もう一回!」「惜しい!」「次頑張ろう!」などの励ましや、「もっと大きくまわした方がいいんじゃない?」「もう少し距離近くしてみる?」などのアドバイス。運動する時は、体を動かすだけでなく、頭で思考することもとても大切です。そして、コミュニケーションをとることもとても大切。ただ体を動かすだけじゃなく、頭も使い、互いに伝え合うことで成功に近づいていくことができました。

最後に中なわをしました。8の字跳びだけでなく、いろいろなバリエーションを紹介していただきました。さらに、2本の中なわを十字にして同時に回したり、最後にはダブルダッチをしたりもしました。初めて体験する受講生も多かったようですが、上手に跳べる受講生が続出しました。それも積極的なコミュニケーションが大きく、成功した時の拍手や盛り上がりもすごかったです。できなかったことができるようになる喜びや達成感は、大人になっても感じられることを改めて実感できたのではないでしょうか。もちろん、それは子どもも同じです。一人でも多くの子どもやクラスが喜びや達成感を感じられるよう、今回の講座を基にどんな手立てが必要か、今後考えていって欲しいです。


今回の講座のクライマックスは全員で8の字跳び。連続で何回跳べるかに挑戦しました。みんなで立てた目標は160回。初めは50回もなかなか超せないことが続きましたが、140回の記録が一度出ました。その時も大きな盛り上がりが生まれましたが、目標に届いていなかったことから、間髪入れず再チャレンジ。ここまで約2時間なわ跳びをして疲れていたと思いますが、目標に向かってみんなで一体となって頑張りました。そして、120回、130回、140回、150回・・・となり、「おぉっ!」といういよいよ感が出る中、また、引っ掛かるかもしれないという緊張感の中、160回達成!今日一番の盛り上がりと一体感が生まれました!しかし、その後も跳び続け、最終的には300回という大記録が生まれました!!これには金森先生も驚いてらっしゃいました。

大きな疲労感を感じる中、それを超える達成感と一体感を感じてくれたのではないでしょうか。受講生の皆さんにとって、自分で体験できたことが大きいと思います。振り返りでもお話ししましたが、このような雰囲気を学校現場で生み出してほしいと思います。
次回は11月29日、テーマは「プレゼンテーション」です。
次回も学び多い講座となるよう、頑張りましょう!