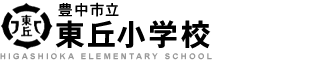これだけ暑くても…
9月に入っても酷暑が続く毎日。
近年稀にみる猛暑下での中秋の名月。
これは、ご存じの通り、陰暦(月の暦)8月15日と9月13日にお出ましになる月を愛でる行事で、中国の風習に習って平安時代に始まり、宮中で詩歌管弦の催しが行われたものです。江戸時代には、庶民の間でも盛んになり、薄(すすき)と秋草を生け、団子、枝豆、里芋、栗、柿などを供えるようになったと言われております。(百科事典マイペディアより)
暑過ぎて今のところ薄はお目見えしませんが、そんな中、本校敷地内(職員室裏手)にひっそりと咲いているものがありました。
何を隠そう、彼岸花です。
この花は有毒ですが、鱗茎(玉ねぎなどのような地下茎)は石蒜(せきさん)といい薬用・糊料(のり・接着剤の類)として有用であるらしいです。(広辞苑より)
毎年当たり前のようにお出ましになりますが、我々の教育活動は当然の如くの前年踏襲だけではなく、少しずつ工夫しながら実情に応じて変化させていきたいものです。
登録日: 2024年9月22日 /
更新日: 2024年9月22日