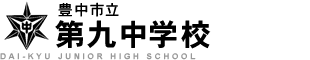1月23日 205号 冬の風物詩持久走 ~体力・気力・努力の向こうに(2年)~
 「金栗四三と持久走と九中走」
「金栗四三と持久走と九中走」
千里 九「学校体育の中で行なわれる持久走は、生徒にとって走るのがスキだ!いや嫌い!と二分する種目である。」
|
|
|
|
|
スタート。自分との勝負だ (写真1) |
15秒、16秒、17秒!(写真2) |
昨日の自分に挑んだ結果は?(写真3) |
体育 「持久走 」 「走る」。今、体育の授業で走っています。2年生は2月におこなわれる合唱コンクールに向け、「ええ声」で歌うため、息切れをおこさぬよう走っているかは定かではありません。言えることは、持久力がつくと”息をたっぷり吸う、はく力”がつきます。すーすーはー。自然と「ええ声」がでるようになるのです。また汗をかくことで代謝が良くなり、「低体温予防」にもつながります。
今、持久走といえば・・・がってんだ。いだてんだ。
今、持久走といえば、金栗四三(かなくりしそう)である。東京オリンピックを翌年に控え、NHKが制作した大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺~」の主人公だ。彼は日本マラソンの父といわれ学校までの往復12㎞を毎日走って登校していたそうだ。
さて、長い距離を走る運動は肉体的負担が大きい。しんどい。この寒い中で走って風邪でもひいたらどうするの?だが、そこを乗り越えたらメリットも大きい。肺が健康になる、ハイ!身体に酸素を取り込む力が大きくなる。肥満予防にもつながる。 日常生活で言えば疲れにくくなり風邪をひきにくくなるのだ。また持久走がほかの種目とちがうのは自分のペースで走るので競わない。つまり「ライバルは昨日の自分」なのだ。
今、持久走といえば・・・今日の自分 越えて明日へと 走る冬
「ライバルは昨日の自分」。2年男子体育では運動場につくった1周約300mのコースを8周(約2,4km)走っている。晴天のなかの九中走だ(左写真)。東は男子テニスコートから西はハンドコートまで走る。このコースを走ってタイムを4回計測するのだが、速い生徒は9分台で走ってくる。
持久走をするにあたってはクラスを2つのグループに分けた。走るのがスキでタイムがいい組と、走るのは苦手だけどタイムをのばそ組だ、持ちタイムが近いので競いあいやすい。で、二人一組をつくる。一人は走り一人はTIMEの計測をおこなう。スタート!(写真1) してゴールラインを通過するたびに、ペアの生徒が1周ごとのラップタイムを記録する。生徒「あと5周!、15、16、17秒!(写真2)」「がんばれ、ラスト!」「いいペース」「(前回と比べて)10秒遅れてる!」と叱咤激励の声もとぶ。生徒は走っていくうちに1周のペースをつかむ。
走ることが楽しめるようになった人は逆境にも強くなる。金栗四三選手は言う「体力、気力、努力」。いだてんの言葉だけに重みがある。体力、気力、努力で一定のラップを刻み、自己記録更新を目指すのだ。
教科担当者「何回か走ってくると、ラップをどの位で刻めばいいか自分で考え自己記録更新が見えてきます。記録を更新すれば達成感にもつながります。またペアの声かけや応援を大事にして頑張りきれる生徒を育てたいので、授業の最後には、自分の走りについて振り返り(写真3)、次の持久走に生かすようにしています。」
韋駄天や 冬はつとめて 駈けぬける